名言集 ジョン・スチュアート・ミル
(イギリスの哲学者,政治哲学者、経済思想家)
私はただ欲を満たそうとするのでなく、それを制限することによって自らの幸福を追求することを学んだ。


名古屋市熱田区のアロマセラピーサロン
名言集 ジョン・スチュアート・ミル
(イギリスの哲学者,政治哲学者、経済思想家)
私はただ欲を満たそうとするのでなく、それを制限することによって自らの幸福を追求することを学んだ。

「将来のことを考えずに好きなことばかりしていると、後で困ってしまうよ」と、子供の時に当たり前に捉えられていた「アリとキリギリス」のお話も、大人になってもう一度読み返してみると、色々と考えさせられることがあると思いませんか?

受け取り方は様々なはずです。例えば、西洋のパターンの所で書いた「やりたい放題やって困ったら、我慢して真面目に頑張ってきた人に泣きついて助けを求める。」
このような捉え方だけじゃなく、元々セミでもキリギリスでも、歌う事が仕事かもしれません。
それと同じように、アリもまた食料を集める事が仕事かもしれませんよね?
どちらも自分の「習性や本能」(人間で言えば自分の本心)に従い「精一杯生きてきた」、そう捉える事も出来るかもしれませんよね?

「他者への思いやりと許す心」「人生全ては自己責任、自分で蒔いたものは何れ自分が狩り取るしかない」「今を楽しんでいれば後悔しない。たとえ死ぬ時でさえも心に余裕がある」。
うーん、3つのラストがあると知れば、更に色々と考えも広がり、「何が正しい生き方で何が正しい教えとは言えなくなってしまう」と思うのは私だけでしょうか?
さて、あなたならどのラストを選びますか?(笑)
最後のバージョンの「もう歌うべき歌はすべて歌ったよ。じゃあ、君は僕の亡骸を食べて生き延びればいいよ」 これは、元の話が「アリとセミ」だったからのようです。それがイギリスに伝わった時、イギリスの方達にとってはセミはあまり重要視されない虫だったようで、キリギリスが取って代わったようです。
これは、元の話が「アリとセミ」だったからのようです。それがイギリスに伝わった時、イギリスの方達にとってはセミはあまり重要視されない虫だったようで、キリギリスが取って代わったようです。
この理由は言語体系の違いからくるもので、日本のように「蝉の声」とセミ自体を認識することなく、雑音として認識すること、更にイギリスのセミは小さく目立たないという特徴、生息域も限られている等もあって、重要視されない虫だったからのようです。 ちなみに東欧ではキリギリスがコオロギ、ロシアではアリがトンボになっていることが多いようです。
ちなみに東欧ではキリギリスがコオロギ、ロシアではアリがトンボになっていることが多いようです。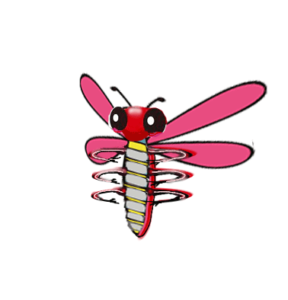 元がセミなら、「もう歌うべき歌はすべて歌ったよ。じゃあ、君は僕の亡骸を食べて生き延びればいいよ」とキリギリスが言った言葉も腑に落ちますよね。
元がセミなら、「もう歌うべき歌はすべて歌ったよ。じゃあ、君は僕の亡骸を食べて生き延びればいいよ」とキリギリスが言った言葉も腑に落ちますよね。
このラストのパターンでは「人生楽しむだけ楽しんだんだから、後は食われて餌になっても仕方ない」みたいな潔さも感じられます。生き方としての良し悪しは解りませんが、この潔さは私は好きです。(笑)

次の「夏は歌って過ごしていたのだから、冬は踊って過ごせばいいんじゃない?」のパターンは、想像出来ると思いますが西洋(ヨーロッパ)の価値観ですね。
「努力しなかったものが大変な思いをするのは当たり前。それを助けるものはいない」。全ては自己責任という教訓と同時に、他者に対しての冷たさも感じとれます。
しかし、現実を生き抜く上で優しさや正しさ、綺麗事ばかりでは済まないのは、大人になり社会で生きていけば当たり前ですよね。これがなかなか抜けないほど生き辛く、悩みも増えるのも事実でしょう。子供の頃からこの「自己責任」と「他者は助けてくれない」、「自分で何とかしないといけない」事を教えるのも必要かもしれません。 同時に、やりたい放題やって困ったら、我慢して真面目に頑張ってきた人に泣きついて助けを求める。それで助かってしまえば、私ならまた同じ行動をとるのでは?とも思います。「それで改心したから次から頑張る」って、簡単にいくのでしょうか?
同時に、やりたい放題やって困ったら、我慢して真面目に頑張ってきた人に泣きついて助けを求める。それで助かってしまえば、私ならまた同じ行動をとるのでは?とも思います。「それで改心したから次から頑張る」って、簡単にいくのでしょうか?
いかないとは言い切れませんが、「それだけではなかなか難しいかな?」とも思ってしまいます。
さて、これまで見てきた3つのパターンですが、「食べ物をくれるパターン」は言わずと知れた日本バージョンですね。慈悲深いと言えば慈悲深いし、甘いと言えば甘いとも採れます。
困っている人を助けるのは当たり前で、例えそれが自分の行いが悪くてその事態を招いたものでも、反省すれば暖かく助けてあげようとする日本人の優しさと同時に、甘さも伺えます。 更に、読み方によってはこうも採れます。アリはキリギリスに「食べ物をあげる代わりにバイオリンを聴かせてほしい」と言いました。そこには「キリギリスが惨めにならないように」という、日本人ならではの気配りも感じさせてくれます。
更に、読み方によってはこうも採れます。アリはキリギリスに「食べ物をあげる代わりにバイオリンを聴かせてほしい」と言いました。そこには「キリギリスが惨めにならないように」という、日本人ならではの気配りも感じさせてくれます。
また、この事を他の視点で捉えてみても、自分の得意なものがあれば、それを用いることで「困った時でも生き延びられるのでは?」って事も考えられるでしょう。
もう一つが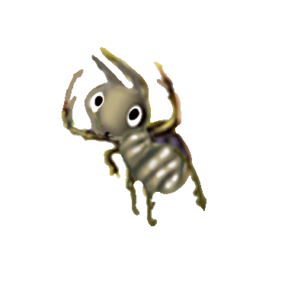 「夏は歌って過ごしていたのだから、冬は踊って過ごせばいいんじゃない?」
「夏は歌って過ごしていたのだから、冬は踊って過ごせばいいんじゃない?」

それを聞いたキリギリスはこう答えました。

「もう、歌うべき歌はすべて歌ったよ。じゃあ、君達は僕の亡骸を食べて生き延びればいいよ」
日本改訂版の多くはこんな感じですよね。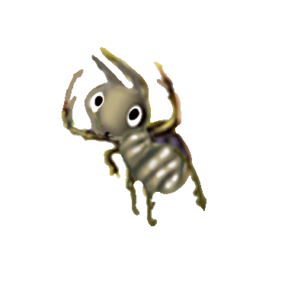 「キリギリスくん、これで解ったかな?怠けてばかりいると、後で困ることになるよ。食べ物をあげるから、代わりにキリギリスくんのバイオリンを聞かせてよ」
「キリギリスくん、これで解ったかな?怠けてばかりいると、後で困ることになるよ。食べ物をあげるから、代わりにキリギリスくんのバイオリンを聞かせてよ」

キリギリスは涙をこぼしながらバイオリンを弾きました。
そしてキリギリスはアリの優しい気持ちに心を打たれ、次の年の夏からは、真面目に働くようになったそうです。
これが日本で改定された物語で、日本人の他者に対しての優しさや慈悲深い精神が伺えますよね?
同時に、「困った時でも誰かが助けてくれるのでは?」という甘さも日本人の心には伺えるのでは?と言う方達もみえるようです。
では、日本で改定される以前の物語ではどうなんでしょう?
二つのパターンがあるようです。
一つが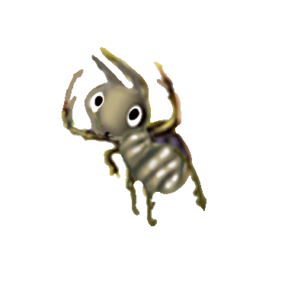 「夏は歌って過ごしていたのだから、冬は踊って過ごせばいいんじゃない?」
「夏は歌って過ごしていたのだから、冬は踊って過ごせばいいんじゃない?」

そう言うと、扉を閉めてキリギリスを追い返しました。そしてキリギリスはアリの家の前で凍え死んでしまいました。

ある夏の日の事、キリギリスは楽しそうにバイオリンを弾き、歌を歌って過ごしていました。
キリギリスは、自分は楽しく過ごしているのに、遊ばないでせっせと働いているアリを不思議に思いました。

そこでキリギリスはアリに尋ねました。
「アリ君は何故、働いてばかりいて遊ばないの?」
アリは言いました。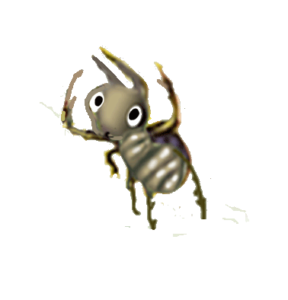
「今のうちに働いて食料を蓄えなければ、冬に食べ物が無くなってしまうからその時に困るんだよ」
キリギリスは馬鹿にしたように言いました。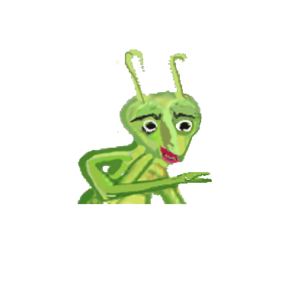 「そんな事言ってたら何時楽しむんだい?そんなことは冬になってから考えればいいんだよ」
「そんな事言ってたら何時楽しむんだい?そんなことは冬になってから考えればいいんだよ」
そして夏が終り、秋になりました。

それでもキリギリスは遊んで暮らしています。
そしてとうとう冬が来ます。

アリの言った通り食料は無くなり、キリギリスはとてもお腹が空いてしまいました。
キリギリスは「何処かに食べ物があるはずだ」

しかし、辺りをくまなく探すものの、周りには食べ物はありません。
「どうしよう?」
キリギリスは困り果てました。
「そう言えば、アリ君達は食べ物を集めていたな」
キリギリスはアリ達が食料を集めていたことを思い出しました。

「アリ君の所へ行ってみよう」
もしかしたら何か食べ物を分けてもらえるかもと、アリ達の家を訪ねました。

「アリ君、何か食べ物があったら分けてくれない?」
キリギリスは食料を分けてほしいとアリに頼みました。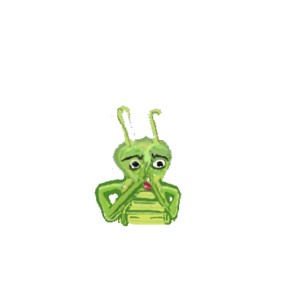 アリは答えました。
アリは答えました。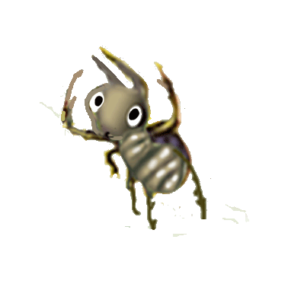
もうすぐクリスマスですね。
みなさんはクリスマスにはどのようなイメージをもっていますか?
イエス・キリストの誕生を祝う祭ですね。
今日では、歴史学的にはキリストが生まれたのが12月25日というのは疑わしく、キリストの誕生祭が12月25日というのはちょっと無理があるかな?と思います。
現在では「キリストが生まれたのは初夏頃ではないか?」「いや5月だ」「いや3月」と、色々と諸説があるのですが、本当のところはどうでしょうね?

では、「12月25日は何だったのか?」
これは古代ローマで隆盛したミトラ教の主審である太陽神ミトラ(ミスラなど)の誕生祭でした。
当時のローマ帝国では冬至の12月25日に祝う習慣が既にありました。そこで、キリストの生誕を祝うクリスマスを重複させることにより、キリスト教を多くの人に浸透させる思惑があったのかもしれません。
しかし、太陽神を主神とするミトラ教は「太陽が出ているのが最も短い日(冬至)」、即ち「太陽が生まれた日」を誕生祭(光の祭り)としました。
当時はキリスト教よりもミトラ教の方が多くの人に信仰されていたと言われています。
実際にミトラ教の協議は、キリスト教の教義の中に数多く取り入れられています。例えばキリスト教の司祭冠を「ミトラ」と言います。三位一体も、12使徒も・・・
また、ローマのバチカン市国の地下墓所にはミトラに捧げられた祭壇が隠されているとも言われています。

それはさておき、日本にもこのミトラ神(ミスラ神)は伝わっています。日本では弥勒菩薩と言われている仏ですね。
釈迦の死後56億7千万年後にこの世に現れ、釈迦の教えでは救われなかった人達を救うと言われる仏ですね。
古代のインドではマイトレーヤと言われていました。

クリスマスがキリストの誕生日ではなかったとしても、同じ「救世主」としてのマイトレーヤの生誕を祝う日だと思えば、やはり祝う気持ちにもなってしまいます。がいかがでしょうか?(笑)

しばらく行くと、村の人であろう母親達が集まっているのが見えてきます。

母親達に親子が近づくと、何やらこちらを見て話をしています。

「あれ見てよ、何てひどい親なの!子供を歩かせて平気なのかしら?」
「自分だけ楽をして子供を歩かせるなんて、考えられないわね。ロバに乗りたいなら子供も乗せてあげればいいのにねー」
「そうよ!二人で乗ればいいのに、馬鹿じゃない?」
それを聞いた男は思いました。
「確かに、そう言われてみればそうだな」と。
今度は子供と二人でロバに乗り、親子は町へ向かって歩き出しました。

しばらく行くと、今度はやっと町が見えてきました。その町の入口の川に架かった橋の修理をしている大工達が見えてきます。

大工達に親子が近づくと、何やらこちらを見て話をしています。

「おいおい、あの痩せたロバに二人も乗るなんて、ロバがかわいそうだろう」
「まったくだ。あんなに苦しそうに歩いているのに、何とも思わないのかね」
その大工の中の一人が「もっとロバを楽にしてやったらどうか?」と、男に言いました。
男は「確かに、そう言われてみればそうだな」と、その大工から余った棒をもらい、狩りの獲物を運ぶように、1本の棒にロバの両足をくくりつけて吊り上げ、それを息子と二人で担いで歩いていきました。

しかし、不自然な姿勢を嫌がったロバが暴れだしました。不運にもそこは橋の上であった為に、ロバは川に落ちて流されていってしまいました。
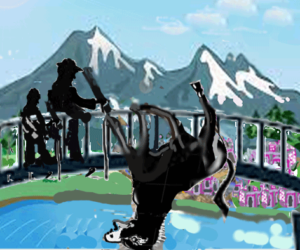
結局、親子は苦労しただけで、全く得しなかったというお話ですね。