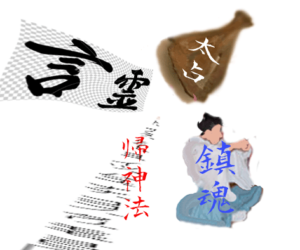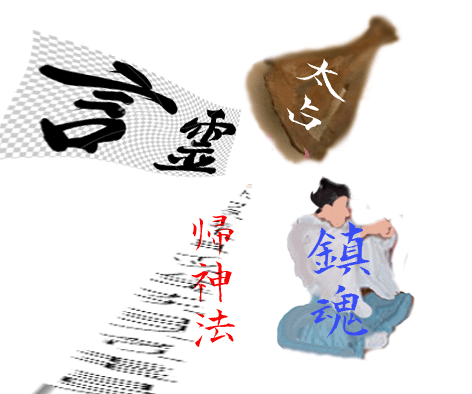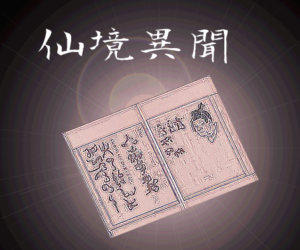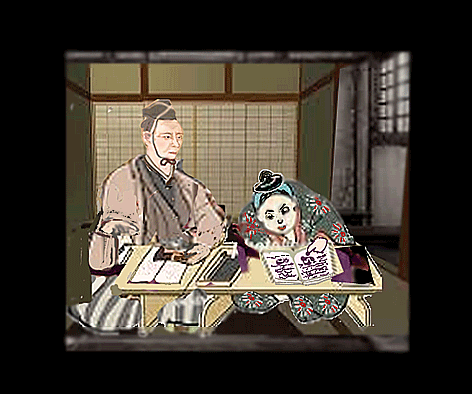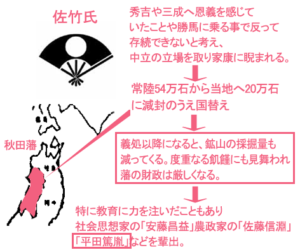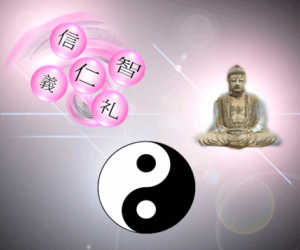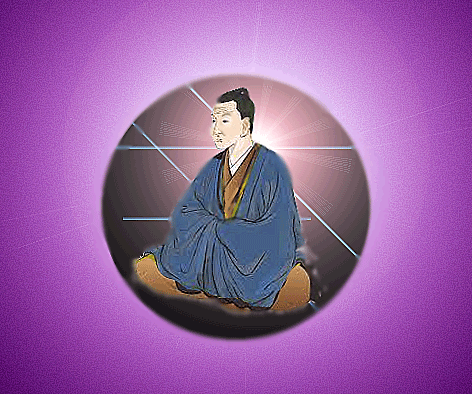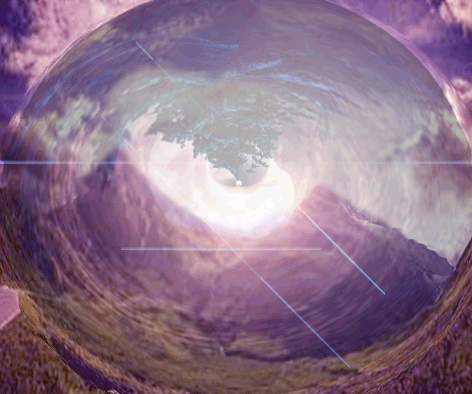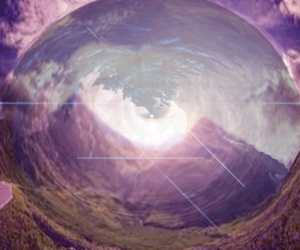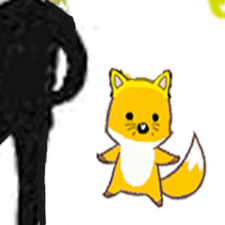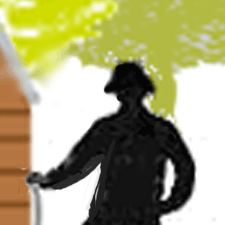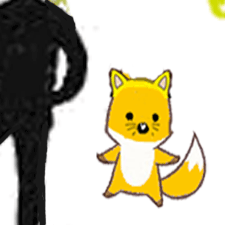もうすぐお正月ですね。
お正月と言えば初詣。神社にお参りに行かれる方も多いと思います。
その神社を中心とした日本の神々への信仰、それが神道ですね。
今回はこの神道(しんとう)についてのお話をします。
しかし、捉え方は人それぞれです。そして実際、誰もが「これが正しい」とは言い切れないほど、多種多様な捉え方があります。
なるべく「こう捉えた方が理解しやすいのでは?」、「後に役に立つだろう」という捉え方で書いていきたいと思います。あくまで「そういう捉え方もあるのか」と思って読んでみて下さいね。
一口に神道と言っても信仰する対象がとても多くあります。
海、川、山、草や木、石など、自然の一部や先祖など、信仰の対象にしたものが色々とあります。
本当に日本には神様がそこらじゅうにいます。(笑)

こういった思想は日本に仏教が入る前からある考えで、ある意味、日本人が培ってきた「日本人の為の宗教ではないのか?」とも言えます。
しかし、現在は一般的に神道と言う場合には「神社神道」のことを指します。
この場合の神道というのは神社への信仰を中心としたもので、それぞれの土地の神社を拝むものです。皆さんが神社にお参りに行かれるのもこれですね。

その中でも圧倒的に数が多いのが宗教法人「神社本庁」が統括する神社です。
この「神社本庁」、もとは内務省の外局であった神祇院の後継的存在です。
しかし庁が付くからといって、現在では官公庁ではありません。民間の宗教法人です。その数は全国に1万8千社あります。
この神明神社の総本社でもあり、日本の約8万社の神社を包括しているのがこの宗教法人「神社本庁」という事になります。
そして古来より「伊勢神宮」を全国の神社の総親神として本宗と仰ぎます。
要するに、これらの神社の頂点が「伊勢神宮」というわけです。
その頂点である神社(内宮)には、神道の神々の中では最高位に位置する太陽を神格化した「天照大神」が祀られているということです。
「あっ、だから皆、お伊勢さん行くのか?」と言う声が聞こえてきそうですね(笑)