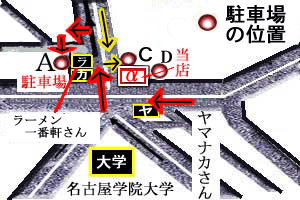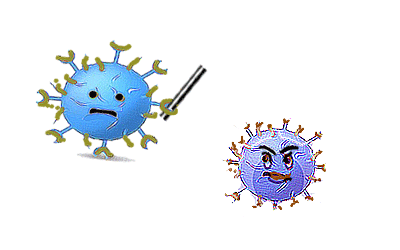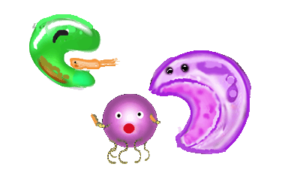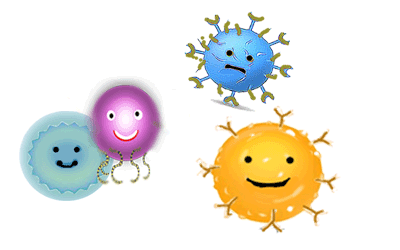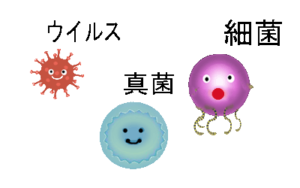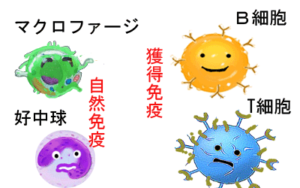前回の「受け取る方がどのように受け取るか」に続いて書いていきます。
迷惑でも迷惑と言えないタイプの人もいる、嬉しくても照れくさいので上手く表せないタイプの人もいる。
また、ストレートに聞いたほうが良いタイプの人もいれば、逆に直接聞くのは避けたほうが良いタイプの人もいるでしょう。

普通は言葉だけで理解しようとするより、その奥にある「表情などの、言葉の裏に隠されているもの」を読み取ることも必要となるでしょう。
そういうものに敏感な方もみえるし、鈍感な人もいます。敏感だからその人の気持ちを読み取れるか?と言えば、そうとばかりも言えません。感情の動きが解っても、その人が何に反応してその感情が動いたかまでは解らないので、反って誤解してしまう場合もあります。
また、その人自身の個別の癖もあるため、よくある「心理を読み解くしぐさ」などが当てはまらなかったり、間違えた解釈もしてしまいます。
対人関係が得意でない人は読み取る能力を知るよりも先に、相手のタイプや自分のタイプを知り、その上でどういうコミュニケーションを取るかを先に考えたほうがいいかもしれませんね?
どのようなタイプの人かを知るのには色々あります。
次回は使えそうで信頼できそうなものを書いていきたいと思います。